開催予定イベント
近日開催予定のフィギュアスケートイベントをご紹介します。練習会から大会まで、様々なイベントにご参加ください。
みんなのコメント

フィギュア中井亜美が練習公開 五輪は「夢から目標に」:北海道新聞デジタル
フィギュアスケート女子で17歳の中井亜美(TOKIOインカラミ)が28日、千葉県内の練習拠点で取材に応じ、来年2月のミラノ・コルティナ冬季五輪へ「夢から目標に変わっている。(初代表に)選ばれたい気持...

【フィギュア】島田麻央、ファイナルへ向け「自信」のV「今シーズンの中で一番変な緊張をせずに楽しめた」 連続ジャンプもばっちり 愛知県競技会ジュニア女子(中日スポーツ) - Yahoo!ニュース
◇28日 フィギュアスケート 愛知県競技会第1日(名古屋市・日本ガイシアリーナ)=中日新聞社後援 ショートプログラム(SP)の得点で競うジュニア女子は、今季の全日本ジュニア選手権で大会史上初の大
https://www.jiji.com/jc/article

氷上エンターテイメント集団が福岡に参上!滑走屋
株式会社ユニバーサルスポーツマーケティング11月29日(土) 12:00より、いよいよ一般発売開始!! ~今までの「フィギュアスケート」のイメージをぶち壊すスタイリッシュで鮮烈な怒涛のノンストッ

【フィギュア】岡田芽依、練習してきた振り付け「点数にもつながった」 手応えの2位 連戦の疲れ残る中「ノーミス」 愛知県競技会ジュニア女子(中日スポーツ) - Yahoo!ニュース
◇28日 フィギュアスケート 愛知県競技会第1日(名古屋・日本ガイシアリーナ)=中日新聞社後援 ショートプログラム(SP)のみで競うジュニア女子が行われ、4日から名古屋・IGアリーナで行われるジ

フィギュアGPファイナル、メダルのリボンに有松・鳴海絞採用 名古屋で12月開催:中日新聞Web
12月4~7日にIGアリーナ(名古屋市北区)で開かれるフィギュアスケートのグランプリ(GP)ファイナルに向けて、愛知県や名古屋市などで...

【フィギュアスケート】同志社大学出身「あゆルカ」ペアが誕生 一時引退も異例の再挑戦|京都新聞デジタル 京都・滋賀のニュースサイト
フィギュアスケートのペアで、異例の再挑戦をするカップルが誕生した。籠谷歩未(同大出)本田ルーカス剛史(同大、綾羽高出)組=木下アカデミー=…

【フィギュア】坂本花織のライバル アンバー・グレンを米メディアが評価「自信に満ちた様子を」 | 東スポWEB
フィギュアスケート女子で2024年グランプリ(GP)ファイナル覇者のアンバー・グレン(米国)に...

フィギュア界を駆け巡った結婚発表は「想像以上の反響」 報告した本人&妻「とても驚いて…」
フィギュアスケートの平昌五輪代表・田中刑事さんが27日、自身のインスタグラムを更新。自身の31歳の誕生日だった22日に結婚を発表していたが、その反響の大きさに「夫婦ともどもとても驚いております」とつづった。

【フィギュア】トゥクタミシェワ 年齢制限の引き上げに「長いキャリアを見たら正しい」=ロシア報道(東スポWEB)|dメニューニュース
フィギュアスケート女子で2015年世界選手権覇者のエリザベータ・トゥクタミシェワ(28=ロシア)が…

「後悔しないように…」演技直後、涙の跡が残った友野一希(27歳)が記者陣に見せた覚悟「うまいから点数が出る競技ではない」「あとは信じ切る力」(田村明子)
11月14日、ニューヨーク州北部レイクプラシッドで開催したGP5戦目、スケートアメリカ。男子は友野一希がSPで1位スタートしたが、翌日のフリーではジャンプミスが出て最終結果3位となった。ベテランのケヴィン・エイモズが初のGPタイトルを手にし、

金沢純禾、1年目で4位「うまい選手がいる中で、すごくいい経験」 ジュニアGPファイナルは「楽しくのびのびと滑って、頑張りたい」【全日本ジュニア選手権女子フリー】 - フィギュアスケート専門情報サイトDeep Edge Plus 最新ニュース・充実のコラムをお届け
フィギュアスケートの全日本ジュニア選手権最終日は24日、東京辰巳アイスアリーナで行われ、女子は島田麻央(しまだ・まお)(木下グループ)が合計196・78点で5年連続5度目の優勝を果たした。岡万佑子(おか・まゆこ)(木下 […]

加生姉妹が国民スポーツ大会フィギュア予選会へ 大分県勢26年ぶり本大会目指し「悔いがないように滑る」 - 大分のニュースなら 大分合同新聞プレミアムオンライン Gate
常設のスケートリンクがない県内でフィギュアスケートに取り組む加生捺乃(かしょう・なつの)(大分高3年)と乙夏(おとか)(王子中3年)の姉妹が、今冬の国民スポーツ大会につながる予選会(29、30日・滋賀)に臨む。

明るい笑顔が印象的なスケート少女 村上佳菜子は「らしさ」全開でトップ選手へと駆け上がった (2025年11月27日) - エキサイトニュース
連載・日本人フィギュアスケーターの軌跡第9回村上佳菜子前編(全2回)2026年2月のミラノ・コルティナ五輪を前に、21世紀の五輪(2002年ソルトレイクシティ大会〜2022年北京大会)に出場した日本人...

高橋大輔に去来する思い「最初は無理だと」臨スポ危機乗り越え10年、かなだい舞った - フィギュア : 日刊スポーツ・プレミアム
「大阪府立臨海スポーツセンター創立50周年感謝祭」が21日、大阪・高石市内で行われました。「かなだい」こと村元哉中(30)高橋大輔(37)、練習生OBの町田樹さん(33)田中刑事さん(28)、ゲストの鍵山優真(20)村上佳菜子さん(28)らが参加。アットホームな雰囲気で、お祝いをしました。通称「臨スポ」は耐震工事の必要性から、12年に閉鎖の危機を迎えました。高橋らスケーターたちが募金を呼びかけ、工事費の半額=1億5000万円を集めて、奇跡の存続を果たしました。記念イベントに参加したスケーターが語った「臨スポ」への思いを3回にわたってお届けします。最終回は「かなだいの言葉」です。 - 日刊スポーツ新聞社のニュースサイト、ニッカンスポーツ・コム(nikkansports.com)。

女子混戦 男子は2強 フィギュア代表争い | 沖縄タイムス+プラス
フィギュアスケートのグランプリ(GP)シリーズは22日までのフィンランディア杯(ヘルシンキ)で全6戦が終了し、シリーズ上位6人によるGPファイナル(12月4~6日・名古屋)に日本の女子は4人、男子は2人が進出した。ファイナルの日本勢上位2人はミラノ・コルティナ冬季五輪の代表選考で優位となる。

【フィギュア】ニューヒロイン候補・中井亜美の強みと今後 鈴木明子さん「攻めるのもあり」(東スポWEB)|dメニューニュース
フィギュアスケート界のニューヒロイン候補はミラノの星となれるか――。22日に全日程が終了したフィギュ…

【フィギュア】山田満知子コーチ指導の14歳・星碧波、全日本ジュニアで飛躍 体幹の強さも武器にトリプルアクセルに意欲:中日スポーツ・東京中日スポーツ
◇「羽ばたけ中部勢」 フィギュアスケートのレジェンドである伊藤みどりさんや浅田真央さん、宇野昌磨さんらを育てた山田満知子コーチが指導す...

フィギュアスケートの演技を引き立たせる衣装の力(宮原知子) - 日本経済新聞
今季のフィギュアスケートは11月22日にグランプリ(GP)シリーズ第6戦が終わり、主要選手のプログラムが一通り出そろった。来年2月のミラノ・コルティナ五輪を控えそれぞれが渾身(こんしん)の演目を用意しているが、各選手の衣装からも強いこだわりが見てとれる。印象に残っているのはアイスダンス世界選手権3連覇中のマディソン・チョック、エバン・ベーツ組(米国)のフリーの衣装。闘牛士というテーマに合わせて

本田望結、梅田のど真ん中に登場したアイスリンク『つるんつるん』で初滑り「大阪で遊ぼうと思ったら本人おるやん!」 | SPICE - エンタメ特化型情報メディア スパイス
2025年11月22日(土)に、グランフロント大阪 うめきた広場にて『ラグザス presentsウメダ☆アイスリンク つるんつるん』がオープンした。 開幕前日に行われたリンク開きセレモニーでは、俳優、フィギュアスケーターとして活躍中の本田望結が登場した。上下デニムのカジュアルなスタイルで颯爽とリンクに現れ、初滑りを披露。開幕にあたり寄せられたコメントを紹介する。 ●本田望結 コメント (c)MBS Q.今年のつるんつるんの滑った気分はいかがでしたか? 今年も最高です!今回で12回目の出演ということで、干支が1周したとスタッフさんと語っていました。 Q.12年前と比べて感想をお聞かせください。 12年前は背が低かった分フェンスの...
https://xn--sp196-x63dvi117tq5is2mh8joj7ebwycur4bteq.xn--78-gb4ao27lf1bl99e

島田麻央が史上初の5連覇 フリーは岡万佑子トップ 男子は4回転ジャンプ3度成功の中田璃士V2 全日本ジュニア選手権最終日 - フィギュアスケート専門情報サイトDeep Edge Plus 最新ニュース・充実のコラムをお届け
フィギュアスケートの全日本ジュニア選手権最終日は24日、東京辰巳アイスアリーナで行われ、女子は島田麻央(しまだ・まお)(木下グループ)が合計196・78点で5年連続5度目の優勝を果たした。5連覇は史上初。ショートプログ […]

トゥクタミシェワが引退 ロシアのフィギュア元女王:中日新聞Web
【モスクワ共同】フィギュアスケート女子で2015年世界選手権優勝のエリザベータ・トゥクタミシェワ(28)=ロシア=が24日、現役引退を...

ウクライナ出身・安青錦 初優勝から一夜明け会見 大相撲11月場所 | khb東日本放送
大相撲11月場所で自身初優勝を果たした安青錦関が優勝から一夜明け、記者会見に臨みました。 ウクライナ出身力士として初優勝を飾った関脇・安青錦。 21歳8カ月での優勝は史上4番目の若さです。 関脇 安青錦 「鯛もったり、これも楽しかったです。…

GP2連勝の千葉、笑顔の帰国|京都新聞デジタル 京都・滋賀のニュースサイト
フィギュアスケートのグランプリ(GP)シリーズ最終第6戦、フィンランディア杯でGP2連勝を果たした女子の千葉百音(木下グループ)と男子の鍵…

【フィギュア】千葉百音がGP2勝目 12月のGPファイナル進出決めた | 東スポWEB
フィギュアスケートのグランプリ(GP)シリーズ最終第6戦、フィンランド大会最終日(22日、ヘル...

【フィギュア】島田麻央、けがから完全復活!圧巻首位発進「うれしい気持ちでいっぱい」 冷静な17歳が珍しく感情あらわ 全日本ジュニア(中日スポーツ)|dメニューニュース
フィギュアスケートの全日本ジュニア選手権が23日、東京辰巳アイスアリーナで開幕し、女子ショートプログ…
https://xn--sp84-6b4c0fsernsj9dwh4101b350a4h4con1a.xn--99-4e4a096z5r0apol

中田璃士がSP発進「ぶっちぎりで優勝を」全日本ジュニア2連覇王手(スポニチアネックス) - Yahoo!ニュース
フィギュアスケート全日本ジュニア選手権の第1日が23日、東京辰巳アイスアリーナで行われ、男子SPでは2連覇を目指す中田璃士(TOKIOインカラミ)が84・99点で首位発進した。トリプルアクセルなど
https://xn--sp64-963czczed03ayhet8xjaa5izizrliw944crnoamx5bq7ip47duxgozzpy7d516ad19ap5k.xn--373-c83b2a4c7a7c7vm63x62zd5v1cpzya

【フィギュア】鍵山優真が逆転V、山本草太6位 GP第6戦フィンランド大会/男子フリー詳細 - フィギュア : 日刊スポーツ
フィギュアスケートのグランプリ(GP)シリーズは22日、ヘルシンキで第6戦フィンランド大会が開幕する。日本からは、第4戦NHK杯優勝の鍵山優真(22=オリエン… - 日刊スポーツ新聞社のニュースサイト、ニッカンスポーツ・コム(nikkansports.com)
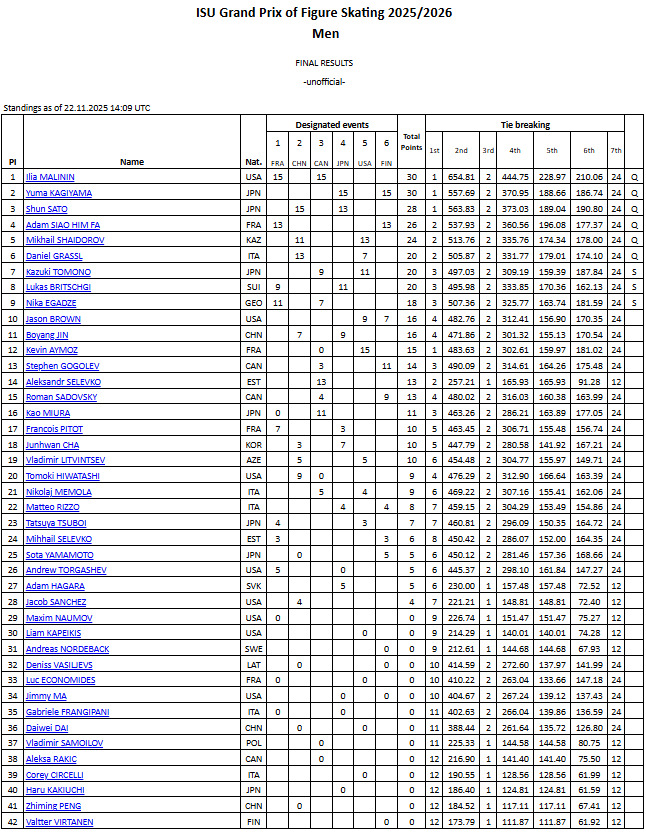
友野一希は総合7位で一歩届かず 鍵山優真、佐藤駿らファイナル進出 男子のGPシリーズ全6戦終了 - フィギュアスケート専門情報サイトDeep Edge Plus 最新ニュース・充実のコラムをお届け
【ヘルシンキ共同】フィギュアスケートのグランプリ(GP)シリーズは22日までのフィンランディア杯で男子の全6戦が終了し、総合成績の上位6人で争うGPファイナル(12月4~6日・名古屋)に日本勢は鍵山優真(かぎやま・ゆう […]

「ゆなすみ」はGPシリーズ2戦連続4位 表彰台に迫る存在感…全日本で五輪代表権に挑戦 - スポーツ報知
ペアのフリーが行われ、ショートプログラム(SP)5位から出た長岡柚奈、森口澄士(すみただ、木下アカデミー)組は、125・59点、合計193・12点で4位だった。

【フィギュア】千葉百音が逆転V、松生理乃は3位 フィンランド大会/女子フリー詳細 - フィギュア : 日刊スポーツ
フィギュアスケートのグランプリ(GP)シリーズ、第6戦フィンランド大会の女子フリーが22日、ヘルシンキで行われ、千葉百音(20=木下グループ)が逆転優勝した。… - 日刊スポーツ新聞社のニュースサイト、ニッカンスポーツ・コム(nikkansports.com)

中田璃士、左足疲労骨折で約1カ月半ジャンプ控える トレーニングで体力ついて「逆に今の方が調子いい」 【全日本ジュニア選手権開会式】 - フィギュアスケート専門情報サイトDeep Edge Plus 最新ニュース・充実のコラムをお届け
フィギュアスケートの全日本ジュニア選手権は23日、東京辰巳アイスアリーナで開幕する。22日に開会式が行われ、男子で2連覇を狙う中田璃士(TOKIOインカラミ)が取材に応じた。7月から親指や甲に痛みがあった左足は疲労骨折 […]

GPファイナル進出が懸かる鍵山優真は3位発進 ジャンプのミスが響き、演技後は固い表情のまま【フィギュア・フィンランディア杯】:中日スポーツ・東京中日スポーツ
◇21日 フィギュアスケート グランプリ(GP)シリーズ第6戦・フィンランディア杯(ヘルシンキ) 男子ショートプログラム(SP)が行わ...
https://xn--sp67-c73cke6b6a3aad8uwa03b7krab89bxbyczgtd0te3942szmkvh8afy7g95tbgh0f.xn--535-c83bwc2at7a1085dr3vd

【フィギュア】〝ゆなすみ〟は5位発進 複数のミスに悔しさも表彰台圏内 3位と2・66点差(東スポWEB) - Yahoo!ニュース
フィギュアスケートのグランプリ(GP)シリーズ第6戦フィンランド大会、ペアのショートプログラム(SP)が21日に行われ〝ゆなすみ〟こと長岡柚奈、森口澄士組(木下アカデミー)は、悔しい滑り出しとなっ

20歳の千葉百音、大躍進の裏に「世界一のコーチ」との絆 恩師とともに歩む夢舞台への道<フィギュア>(テレ朝POST)|dメニューニュース
11月21日(金)、フィギュアスケート・グランプリシリーズ第6戦フィンランド大会が開幕する。シリーズ最終戦…
https://xn--sp81-w83cwbwe8ay255dp9mnpcm0jt3d215cp97b6b8b.xn--097-b73bzc5byc0vd2879elqgi97doo3a3x0bci2bfp4a

鍵山優真「すごくいい練習できた」 21日からフィギュアGP最終戦、フィンランディア杯
フィギュアスケートのグランプリ(GP)シリーズ最終第6戦、フィンランディア杯は21日にヘルシンキで開幕する。20日は公式練習が始まり、男子で第4戦を制した鍵山…

【フィギュア】“ゆなすみ”「メダルを第一目標」初のGP表彰台へ 21日フィンランド大会開幕 - フィギュア : 日刊スポーツ
【ヘルシンキ(フィンランド)20日=松本航】フィギュアスケートのグランプリ(GP)シリーズ最終第6戦フィンランド大会は21日、ヘルシンキ・アイスホールで開幕す… - 日刊スポーツ新聞社のニュースサイト、ニッカンスポーツ・コム(nikkansports.com)

【フィギュア】山本草太「おはらい行った方がいいのか…」腰痛&ぜんそく抱え(日刊スポーツ)|dメニューニュース
【ヘルシンキ(20日)=松本航】フィギュアスケートのグランプリ(GP)シリーズ最終第6戦フィンランド大会は2…

フィギュアスケートのオリンピック代表選考 - フィギュアスケート専門情報サイトDeep Edge Plus 最新ニュース・充実のコラムをお届け
フィギュアスケートのミラノ・コルティナ冬季五輪代表選考 各3枠の男女は最終選考会を兼ねる全日本選手権(12月19~21日・東京)の優勝者が自動的に代表入り。2人目は全日本2、3位やGPファイナルの日本勢上位2人、全日本 […]

村上佳菜子さん、「名古屋フィギュアスケートフェスティバル」にゲスト出演 演者として滑るのは現役時代の2017年以来:中日スポーツ・東京中日スポーツ
新年恒例となっているフィギュアスケートのアイスショー「名古屋フィギュアスケートフェスティバル」(中日新聞社共催)が来年1月4日に名古屋...

4回転武器にGPファイナルへ フィギュア女子の住吉りをん(共同通信)|dメニューニュース
フィギュアスケートで22歳の住吉りをんが21日開幕のグランプリ(GP)シリーズ最終第6戦、フィンランディア…

GP最終戦、鍵山「燃えている」 ヘルシンキで練習:朝日新聞
【ヘルシンキ共同】フィギュアスケートのグランプリ(GP)シリーズ最終第6戦、フィンランディア杯(21日開幕)に出場する日本勢が19日、開催地のヘルシンキで練習し、男子でエースの鍵山優真は「すごく燃え…

日本勢が調整 鍵山優真「300点超え」へ意欲 GPフィンランド(毎日新聞) - Yahoo!ニュース
フィギュアスケートのグランプリ(GP)シリーズ最終戦フィンランド大会に出場する日本勢が19日、ヘルシンキのリンクで調整した。16日から現地入りしていた男子の鍵山優真選手(オリエンタルバイオ・中京大

鍵山優真「最低300点は出さなきゃ」 迫るオリンピックへ、スロースターター脱却の決意【GP第6戦フィンランディア杯・非公式練習】 - フィギュアスケート専門情報サイトDeep Edge Plus 最新ニュース・充実のコラムをお届け
【ヘルシンキ共同】フィギュアスケートのグランプリ(GP)シリーズ最終第6戦、フィンランディア杯(21日開幕)に出場する日本勢が19日、開催地のヘルシンキで練習し、男子でエースの鍵山優真(オリエンタルバイオ・中京大)はサ […]

バスケ渡辺雄太「いい意味で誰が主将かわからぬチームに」 代表合宿|スポーツニュース|TNC
最新の試合結果など、スポーツニュースをお届け。